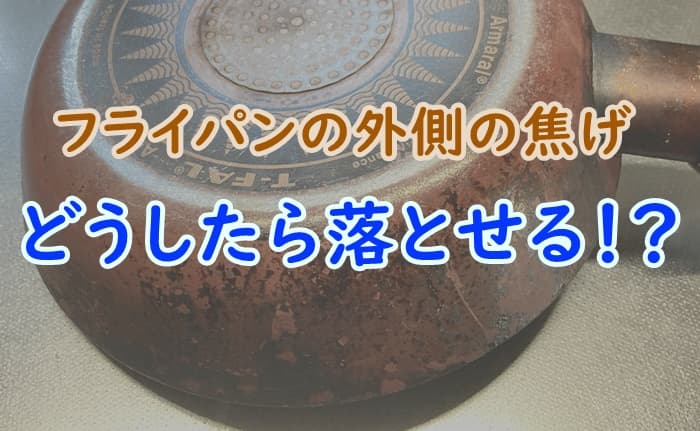いつもフライパンを使ったらきれいに洗っているつもりでも
『いつの間にか裏側が焦げ付いてる!』
なんてこと、ありますよね。
フライパンが焦げ付くのは、内側だけじゃないんです。
外側や裏側にも、焦げが付いてしまうことがあります。
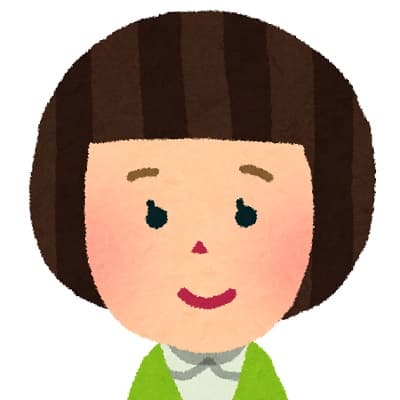
はい、あります。
焦げは軽いうちに対処すれば、わりと簡単に落とせるんですよ!
ということで、この記事では
- フライパンの裏や外側に付いた焦げの落とし方
- フライパンの裏や外側に焦げが付いてしまう原因と防ぎ方
について解説します。
ぜひ読んで、フライパンをきれいにしてくださいね!
スポンサーリンク
フライパンの裏や外側の焦げの落とし方は?
フライパンの裏側、外側の焦げを落とすには
- 焦げ落とし用洗剤を使う
- 重曹を入れたお湯で煮沸する
- 重曹ペーストで磨く
- クレンザーで磨く
- 要らないポイントカードなどでこする
- 天日干しする
という方法があります。
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
焦げ落とし用洗剤を使う
焦げを落とすのに一番手っ取り早いのは、
焦げ落とし用の洗剤を使う
という方法です。
たとえば、
- 焦げ取りぱっとビカ
- 焦げ取り名人
などです。
こういった洗剤を使うと、簡単に焦げが落とせます!
ただし、
- フライパンの材質によっては使えないことがあるので、買う前に商品説明をよく読み、自分のフライパンに使える製品を選ぶ
- 製品の使い方や注意事項をよく確認して、正しい使い方をする
ということを守ってくださいね。
メモ
焦げ落とし用のタワシもありますが、金属のたわしや研磨剤を多く含むタワシは、フライパンの材質によっては傷が付くことがあります。
私としては、焦げ落とし用タワシより洗剤を使うほうがおすすめです。
重曹を使って焦げを落とす方法
酸性の油を多く含む焦げ付きは、アルカリ性の重曹を使って落とすことができます。
重曹の使い方には、
- 重曹を入れたお湯で煮る
- 重曹ペーストを付けて磨く
という2通りの方法があります。
それぞれの方法について、見ていきましょう。
重曹で煮る
焦げ落としにおすすめなのが、『重曹で煮る』という方法です。
用意するもの
- 水
- 重曹(水1Lに対して大さじ2杯くらい)
- フライパンが入るくらいの大きさの鍋(必ずアルミや銅以外の鍋を使うこと)
- スポンジ
- 手袋
手順は、
- 鍋に水と重曹を入れ、フライパンを入れる
- 強火にかけて沸騰させる
- 沸騰したら火を弱め、10~20分くらい煮る
- 火を止めて、1時間くらい放置する
- スポンジでフライパンをこする
- 焦げが落ちたら、重曹をきれいに洗い流す
私もこの方法でやかんの焦げを落としたことがありますが、スルスル落ちて気持ちよかったですよ!
なお、フライパンが入る鍋がないときは、
- ビニール袋にお湯と重曹を入れ、フライパンを浸けおきする
- 耐熱性のたらいにお湯を入れて、フライパンを浸けおきする
という方法でもOKです。
重曹で煮沸するときに注意すること
重曹で煮沸をするときは、
- アルミや銅など、アルカリ性に弱い素材のフライパンには重曹を使わない
- フライパンを入れる鍋も、アルカリ性に強い素材でできた鍋を使う
- 重曹は必ず水から入れる
- 沸騰したら必ず火を弱める
- 沸騰した重曹水はアルカリが強くなるので、手袋をして作業をする
ということに気を付けてください。
アルミや銅は、重曹に反応して変色や変質してしまうことがあります。
フライパンや煮沸に使う鍋がアルミや銅ではないかどうか、よく確認してくださいね。
また、水を沸騰してから重曹を入れたり、強火で沸騰させ続けたりすると、お湯が飛び散ったり吹きこぼれたりします。
やけどする危険性もあるので、『重曹は水が温まる前に入れ、沸騰したら弱火』を守ってください。
重曹ペーストを付けて磨く
重曹は、研磨剤としても使えます。
軽い焦げ付きなら、重曹で磨くだけで落とせることもあります。
用意するもの
- ぬるま湯
- 重曹
- ラップ
- スポンジ(ラップで包んでおく)
- 手袋
手順は
- 重曹をぬるま湯で練ってペースト状にする
- 焦げた部分に塗り、ラップをかけてパックし、30分くらい放置する
- 30分くらいたったらラップを外し、洗い流さずにそのままラップに包んだスポンジでこする
- 焦げ付きが落ちたら、よく洗い流す
重曹の固さは、塗りやすく、流れてしまわないくらいの固さがちょうど良いですよ。
メモ
重曹で煮る方法のところでも書きましたが、
アルミや銅製のフライパンには、重曹ペーストもNGです。
重曹は、フライパンの素材を確かめて使ってくださいね。
クレンザーを使う
重曹でも落ちない焦げ付きには、クレンザーを使ってみましょう。
用意するもの
- クレンザー(研磨率20%くらいのもの)
- ラップでくるんだ柔らかいスポンジ、または丸めたラップ
- ラップ
やり方は、
- クレンザーを焦げた部分に付ける
- ラップで包んだスポンジか丸めたラップで、あまり力を入れずにこする
- よく洗い流す
これだけです。
クレンザーは、研磨率が高いほど研磨剤がたくさん入っています。
でも、研磨剤があまり多いと、傷も付きやすいです。
20%くらいの研磨率の製品を使うのがおすすめですよ。
また、あまり力を入れてこすると、これも傷の原因になります。
あまり力を入れず、根気良くこすってください。
硬い物で削ってこそげ落とす

ポイントカードも焦げ落としに使える!
わりと原始的な方法ですが、
『硬い物でこすって焦げを落とす』という方法もあります。
手順は、
- 焦げた所をしばらくお湯に浸けおきする
- 焦げが少し柔らかくなったら、使っていないクレジットカードや硬いポイントカードなどでこする
ただし、『硬い物でこする』ということは、当然傷を付けてしまう可能性もあります。
- 金属ヘラなど、かなり硬い物は使わない
- あまり力まかせにこすらない
ということに注意してください。
天日干しする
昔ながらの焦げ落とし方法として、『天日干し』があります。
やり方はとてもシンプルで、
- フライパンを1週間くらい、日当たりの良い場所に出して日光に当てる
- 焦げ付きが完全に乾いてパリパリしてきたら、木べらなどで焦げをこすり落とす
という手順です。
『焦げをパリパリに乾かす』ということがポイントなので、
乾かしている間は、雨や夜露、朝露などで濡らさないように気をつけましょう。
天日干しでの焦げ落としは簡単なのですが、
- 時間がかかる
- 雨が降ったら天日干しができないので、何日かかるかは天気まかせになる
- 焦げを落とすまで、フライパンを使えない
ということが、最大のデメリットです。
今は天日干し以外にも焦げ落としの方法があるので、天日干しで焦げを落とす人も少ないでしょう。
でも、実験的にやって楽しむには良いかもしれませんよ。
焦げ落としに使わないほうが良いもの・注意が必要なもの
ネットには、フライパンの外側の焦げ落としに
- オキシクリーンや酸素系漂白剤
- 洗剤入りの金属タワシ
- メラミンスポンジ
といったアイテムを勧めている情報もあります。
でも、
オキシクリーンは基本的にやめておいたほうが良いですし、スチールウールタワシやメラミンスポンジは使い方に注意が必要です。
焦げ落としにオキシクリーンは使える?
フライパンの焦げ落としに、オキシクリーンを使う人もいますが、
公式サイトに『金属への使用はNG』と書いてあるので、おすすめしません。
参考 オキシクリーン 500g/1500g/つめかえ用 1000g/つめかえ用 2000g 詳細ページ
- オキシクリーン以外の酸素系漂白剤
- 注意書きや使い方に『金属には使わないように』と書いてある洗剤
も、やめておいたほうが良いです。
また、オキシクリーンや酸素系漂白剤は
テフロンなどのコーティング加工のフライパンの場合、内側に付くと加工が傷む可能性があります。
オキシクリーンや金属に使えない洗剤を使う場合は、内側に付かないように注意して、自己責任で使ってくださいね。
洗剤や研磨剤入りのスチールウールタワシ
『ボンスター』などの洗剤入りスチールウールタワシも、焦げ落としには役立ちます。
ただし、金属タワシはどうしても傷を付けてしまいやすいです。
フライパンの外側に塗装がしてある場合、強くこするとはがれてしまう可能性があります。
スチールウールタワシを使う場合には、
- 最初に目立たない所でこすり加減などを試してから焦げを落とす
- こするときに力を入れすぎないようにする
- コーティング加工のフライパンは、絶対に内側をこすらない
ということに注意してください。
メラミンスポンジを使う場合
メラミンスポンジは柔らかそうに見えますが、細かい網状になっているから柔らかく感じるだけで、
実はけっこう硬い素材でできています。
なので、メラミンスポンジも傷を付けないように使う必要があります。
メラミンスポンジで焦げを落としたいときは
- 水をたっぷり含ませて使う
- 力を入れずに、なでるようにこする
- コーティング加工のフライパンの内側をこすらない
ということに注意してください。
メラミンスポンジの注意点や使い方は、こちらの記事に詳しく書いてあります。
併せて読んでくださいね。
関連記事:激落ちくんに毒性は本当?メラミンスポンジの正しい使い方と原理を解説
フライパンの外側に焦げが付く原因と予防法

裏も忘れずに洗おう
フライパンの外側や裏に焦げが付く原因
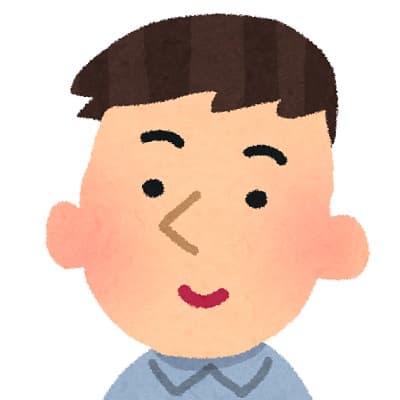
外側や裏にまで焦げが付いてしまう原因は
- 料理中に、油や汁が跳ねて付いた
- 料理を食器や容器に移すときに汁が垂れ、フライパンの熱で水分が蒸発して焦げになった
- 隣の鍋から飛び散ったりこぼれたりした油や汁、食材などがフライパンにくっついた
- フライパンを火にかけたときに、コンロの五徳に付いていた汚れが焼き付いてしまった
- 洗った後に水分を拭き取らずに火にかけたために、水分が蒸発するときに熱が集まり、その部分が焦げた
- フライパンの裏に付いた汚れが洗い流されないままになっていて、調理の時に焦げた
といったことです。
このうち、注意すれば避けられるのは
- きちんと洗えていなかった
- 洗った後に水分をふき取らなかった
- コンロの五徳が汚れていた
ということくらいで、その他の原因は、フライパンを調理で使う以上、気を付けても避けるのは難しいです。
つまり、外側が焦げ付くのも、ある程度は仕方ありません。
フライパンの外側や裏の焦げ付きを防ぐには
フライパンの外側や裏に焦げが付くのを防ぐには
- 普段からコンロの五徳をきれいにしておく
- フライパンの外側に油や汁が付いたら、できるだけ早く拭き取っておく
- フライパンを使い終わったら、外側も丁寧に洗う
- 洗った後に火にかける時は、水分を拭き取ってから火にかける
ということが大切です。
一言で言うと、
フライパンやコンロの五徳はできるだけきれいにし、汚れたときはできるだけ早く取り除く
ということです。
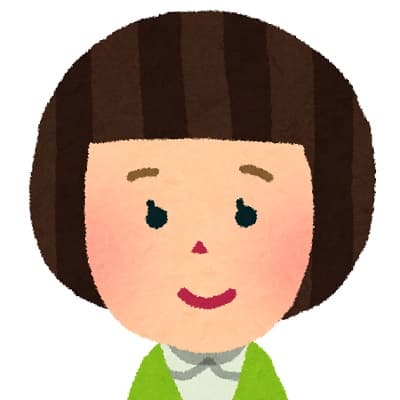
はい、とても基本的でシンプルな方法で、焦げはある程度防げるんです。
でもシンプルなことでも、忙しくて毎日はきちんとできなかったりすることも多いですよね。
無理のない範囲で『いつもなるべくきれいに』を心がけつつ、焦げが目立ってきたら早めに落とせばOKですよ!
スポンサーリンク
まとめ
フライパンの外側や裏側に付いた焦げは、
- 焦げ落とし用の洗剤を使う
- 重曹で煮る
- 重曹ペーストで磨く
- クレンザーで磨く
- 要らないキャッシュカードなどでこする
- 天日干しにして乾かし、こそげ落とす
という方法で取り除くことができます。
|
重曹なら、『なるべく洗剤を使いたくない』という人にも使いやすいですね。
ただし、重曹を使うときには、
- フライパンと煮沸するために使う鍋が、アルミや銅など、重曹に弱い素材ではないことを確認する
- 手荒れを防ぐために、手袋をする
- 重曹で煮沸するときは、重曹は水から入れ、沸騰したら必ず弱火にする
といったことに注意しましょう。
そして、フライパンの外側や裏の焦げは、
- フライパンに油や汁が付いたら、なるべく早く拭き取る
- フライパンを使った後は、外側もしっかり洗う
- 洗ったら、水分をしっかり拭き取る
という方法で防ぐことができます。
内側も外側もきれいにして、気持ちよくフライパンを使ってくださいね!