ガスを使うときに絶対に気をつけなければならないのが
『事故を起こさないようにすること』
ですよね。
特に怖いのが爆発事故!
ひとたび起きると、大きな被害が出てしまいます。
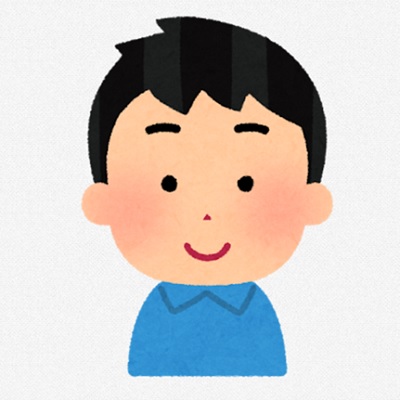
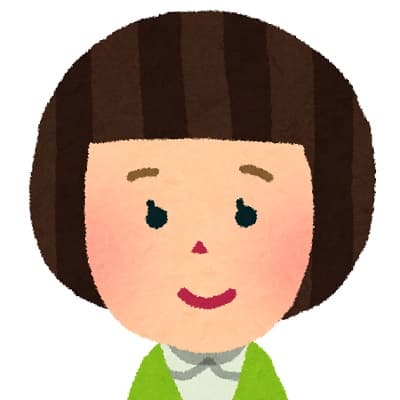
安全に使うためにも、事故の原因や予防法は知っておきたいですよね。
ということで今回は、
- プロパンガスやコンロ、ガスボンベの爆発事故の原因
- プロパンガスの事故を防ぐ方法
について調査しました。
ガスを安全に使うためにもぜひ、じっくり読んでくださいね!
スポンサーリンク
プロパンガスやコンロが爆発する原因は?
プロパンガスが爆発する仕組み
『ガス爆発』と聞くと『ガスが爆発する』というイメージがありますが、プロパンガスが単体で爆発することはありません。
プロパンガスの爆発は
- プロパンガスがある程度の濃度で空気と混ざり、酸素と結びつく
- その状態で、火に接触する
というメカニズムで起きます。
『ガスが酸素と結びついた状態で火に接触する』というのは、たとえば、
- ガス漏れが起きている場所で火気(電気器具や静電気の火花、タバコの火など)が発生する
- ガス器具の中にガスが漏れて充満しているのに気づかず、点火操作をする
といったシチュエーションです。
つまり、爆発事故は漏れたガスに着火して起きるのです。
『たかがガス漏れ』と甘く見ないで、
ガス漏れが起きたときは絶対にガス器具や電気器具を使わず、すぐに換気をして、ガス会社に連絡してください。
メモ
『ガスの爆発』と『ガス器具での正常な燃焼』の違いは、
ガスの爆発
⇒急激な燃焼が起き、燃焼によって急速に空気が膨張して爆発する(燃焼をコントロールできない)
ガス器具での燃焼
⇒空気との混ざり具合やガスの出る量などを調整しているので、燃焼をコントロールできる
という点です。
ガスコンロが爆発する原因は?
次に、
- ビルトインコンロやテーブルコンロ
- カセットコンロ
の爆発の原因について見ていきましょう。
ビルトインコンロやテーブルコンロの爆発の原因
ビルトインコンロやテーブルコンロで爆発や火災が起きる原因も、つまるところは
『ガス漏れ』です。
何がガス漏れの原因になるかというと
- ガス器具の故障や破損
- 火が消えているのに、ガス器具のつまみが『切』や『閉』になっていない(コンロの内部にガスが漏れている)
- ガスホースの亀裂や劣化
- ガスホースと元栓やガス器具をつなぐバンドが緩んでいる
- ガス栓の劣化や故障
- 使っていないガス栓を開けてしまった
といったことです。
上に挙げたようなことが原因で漏れたガスに着火すると、爆発や火災が起きてしまいます。
カセットコンロの爆発や火災の原因
カセットコンロの場合は『ガス漏れ』に加え、
- 複数のカセットコンロを並べて使う
- カセットボンベを設置する部分を覆うような、大きな鍋やプレートを使う
- IHクッキングヒーターなど、電磁調理器の上でカセットコンロを使う
- 石綿やセラミックなどが付いた魚焼き機を使う
- カセットボンベのセットの仕方を間違える
- 古くなって部品が劣化したカセットコンロやボンベを使う
- カセットボンベを直射日光の当たる場所や車内、火の近くなど、温度が上がる場所に置く
といったことでも、爆発や火災のリスクがあります。
カセットボンベが過熱されるような扱い方をすると、ボンベの中のガスが熱せられて爆発が起きてしまいます。
カセットコンロを使うときには
- カセットボンベをセットする部分に鍋やプレートがかからないようにする
- コンロは必ず単体で使い、複数のコンロを並べて使わない
- カセットボンベは正しくセットする
- 古いコンロやカセットボンベは使わない
- カセットボンベは直射日光が当たる場所や温度の上がる場所を避けて保管する
といったことに注意しましょう。
関連記事:プロパンガスのボンベの仕組みと圧力をチェック!爆発の可能性は?
プロパンガスボンベが爆発する原因は?
プロパンガスボンベ本体が爆発することがあるとすれば、
- ボンベの中に空気が入り込み、プロパンガスと酸素が混ざったところに火がついた
- ボンベに急激に強い圧力がかかって押しつぶされた
- ガスボンベが壊れるくらいの、とても強い衝撃がかかった
といったことが原因です。
でも、プロパンガスボンベが爆発することは、めったにありません。
- プロパンガスの中はガスで満たされているので、空気が入ることはまずない
- ボンベには圧力がかかると中のガスを逃がして圧力を下げる仕組みがあるので、よほど急激に強い圧力が加わらない限り爆発しない
- ボンベはとても頑丈にできているので、よほど強い衝撃でなければ壊れない
など、爆発が起きないように作られているからです。
ただし、めったに爆発しないからといって、
絶対に、設置してあるガスボンベをいじったり動かしたりしないでください。
プロパンガス爆発の威力はどのくらい?
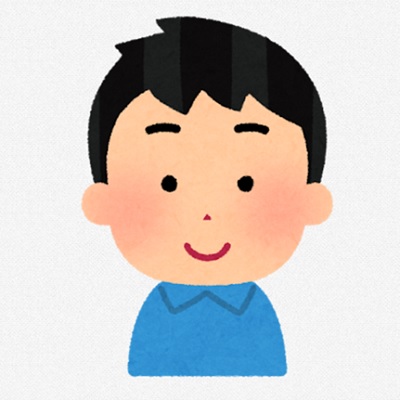
ガスの量や爆発の規模にもよりますが、
一般家庭のプロパンガスの爆発でも、住宅が全壊することがあるくらいの威力
と考えておいてください。
また、プロパンガスの爆発は『小規模ならまだ大丈夫』というわけではありません。
爆発そのものの規模が小さくても、
- 近くの可燃物に火が移って火災が起きる
- 体に火が触れたり服に火が移ったりしてやけどを負う
といった危険性があります。
絶対に甘く見ないでくださいね。
爆発事故に遭遇したら
万が一、爆発事故に遭遇したときは、
すぐにできるだけ遠くに避難し、身の安全を確保してください!
119番に通報する場合も、自分の安全をしっかり確保したうえで通報しましょう。
ガスの爆発事故では、
- 繰り返し爆発が起きる
- 爆発で物が飛んでくる(火が付いた物が飛んでくる可能性もある)
- 爆発の炎が広がる
- 突然、予想もしなかった大爆発が起きる
- 爆発の衝撃で、周りの建物の窓ガラスなどが割れて飛び散る
といった危険性があります。
絶対に、動画や写真を撮ろうなどと考えてはいけません。
周りの人とも声を掛け合って、とにかくすぐに逃げてください。
ガス漏れと爆発以外のガスの事故
ガスの『事故』は、ガス漏れと爆発だけではありません。
不完全燃焼による一酸化炭素中毒も、『事故』の一種です。
家庭用プロパンガスそのものには毒性はありませんが、不完全燃焼で発生する一酸化炭素は、中毒を起こしやすい物質です。
- 頭痛
- めまい
- 吐き気
- 失神
といった症状が出る他に、
最悪の場合は命に関わることもあります。
ガスを使うときは、不完全燃焼にも十分注意しましょう。
プロパンガスの事故を防ぐには

正しい使い方を!
プロパンガスの事故を防ぐためには、
- ガスやガス器具を正しく使う
- 使わないガス栓にはカバーやキャップを付ける
- ガス漏れが起きたときは絶対にガスを使わず、ガス会社に連絡する
- ガス会社による定期点検を必ず受ける
- 緊急対応の体制が整っているガス会社と契約する
- 設置されたガスボンベはいじらない
ということが重要です。
では、具体的にどうすればよいのかを見ていきましょう。
ガス器具の正しい使い方
ガス器具を使う時には、
- ガス器具を買うときは、どんな安全装置が付いているかを確認して買う
- ガスの種類に合ったガス器具を使う
- ガス栓は、使う時には『全開』で使う
- 換気をする
- 点火・消火は必ず目で見て確かめる
- 青い火で使う
- 火が付いているときは必ず近くにいる
- ガス器具の近くに燃えやすいものを置かない
- ガス器具を使い終わったら、ガス栓を確実に閉める(ビルトインコンロや給湯器などを除く)
- ガス器具やガスホースの手入れや点検をする
といったことを守りましょう。
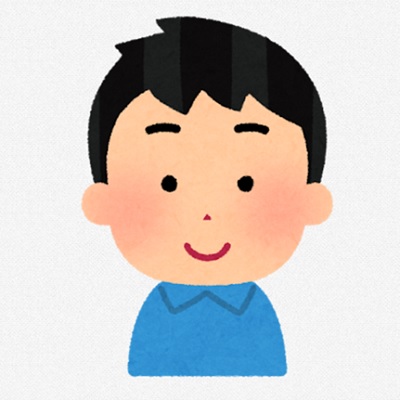
はい、そうです。
『基本的なことをきちんと守って使っていれば、高確率で事故は防げる』ということなんです。
関連記事:ガスコンロの都市ガス用とプロパン用の違いを解説!両用できる?
関連記事:ガスの元栓はどこにあるの?家の中の設置場所をチェック!
使わないガス栓には誤開放防止のカバーを
使わないガス栓には、ゴムキャップと栓カバーを付けておきましょう。
『使っていないガス栓を間違って開けてしまった』という誤開放によるガス漏れを防ぐためです。
ゴムキャップと栓カバーは、こういうものです。

使わないガス栓のカバーとキャップ
上の写真のように、『2口のガス栓のうち、片方しか使っていない』という場合は特に、ゴムキャップと栓カバーの使用を強くお勧めします。
これなら確実に誤開放を防げますよ。
ガス栓カバーは、ネット通販でも買えます。
サイズや選び方がわからない場合は、ガス会社に問い合わせてくださいね。
|
ガス会社の定期点検を受ける
プロパンガス会社には、
4年に1度、ガス設備やガス器具の定期保安点検を実施すること
が義務付けられています。
この点検は、必ず受けてください。
ガス器具の異常や不具合を見つけることで、ガス事故を防ぐことができます。
定期保安点検では
- 外のメーターなどの点検
- ガスコンロやガス栓などの点検
があります。
定期保安点検には立ち合いが必要なので、必ず立ち会える日程で点検日時を決めてくださいね。
緊急対応の体制が整っているガス会社を利用する

頼りになるガス会社を選ぼう!
ガス漏れなどがあった場合には、すぐにガス会社に連絡して、対応してもらう必要があります。
そのため、緊急対応の体制が整っているガス会社を利用することが大切です。
緊急対応はガス会社の『義務』なので、どのガス会社でもきちんと対応してくれるはずです。
もしも
- ガス会社の緊急対応が心もとない
- ガス漏れがあって連絡したが、すぐ対応してもらえなかった
- 保安点検がずさん
など、ガス会社の緊急対応や安全管理に問題や不安がある場合は、ガス会社の変更も検討したほうが良いでしょう。
ガス会社を変える時は、ガス会社変更サービスを利用するのが簡単で確実です。
ガス会社の対応が気掛かりな時は、気軽に相談してみてくださいね。
関連記事:【2022最新】ガス料金を節約するプロパンガス会社変更サービス比較
設置されたガスボンベはいじらない
ガス会社では、プロパンガスボンベを設置するときに
安全にガスを使えるように、基準やルールを守って設置しています。
ですから、
設置されたボンベは絶対にいじったり動かしたりしないでください。
自分の判断でいじったり動かしたりした場合の安全は、担保できません。
また、ガスボンベを固定する鎖やガスボンベのそばにある元栓も、いじってはいけません。
- ガスメーターや元栓、配管などに異常を見つけた
- いつの間にかガスボンベを固定する鎖が外れていた
- ボンベを移動したい・ボンベの置き場所を変えたい
といったときは、必ずガス会社に連絡して指示に従ってください。
関連記事:プロパンガスボンベの設置基準や保管(置き場)のルールを解説!
関連記事:プロパンガスの取扱や運搬に必要な資格をわかりやすく解説!
企業側の事故防止対策
ガス器具やボンベを作るメーカー、そしてガス会社でも、事故を起こさないための努力をしています。
ガスボンベやガス設備、ガス器具などには
ガスボンベ
⇒安全弁などの安全装置
ガスメーター
⇒異常が起きた場合にはガスを遮断する仕組みの安全装置
ガスコンロ
⇒不完全燃焼防止装置や立ち消え安全装置など
給湯器
⇒不完全燃焼防止装置や空焚き安全装置、凍結防止装置など
ガスファンヒーター
⇒不完全燃焼防止装置、転倒時ガス遮断装置、過熱防止装置など
といった安全装置が付いています。
さらに、ボンベを作る企業やガス会社でも
- 定期的なガスボンベの検査
- ガスメーターやガス器具の検査
を行っています。
このように、プロパンガスの事故は二重三重に防ぐ努力がされているのです。
その結果、ガスを使っている世帯に対する事故の割合は、
0.0000088%程度です。
でも、どんなに安全装置を付けたり点検したりしても、
最終的には、使う人がどう使うかが、とても重要です。
ガスやガス器具は、正しい使い方を守って安全に使いましょう!
スポンサーリンク
まとめ
プロパンガスの爆発事故の原因は、
- ガス漏れが起きたところに着火操作や静電気などの火気が発生して、ガスに火が付く
- 漏れたガスがガス器具の内部に溜まって、そこに火が付く
- カセットボンベが何らかの理由で熱せられる
といったことが原因です。
プロパンガスボンベそのものは、よほどのことがない限り爆発することはありません。
でも、ガス会社が設置したボンベは、触ったり動かしたりしないでください。
ガス器具は
- ガス器具やカセットボンベは正しい使い方・扱い方をする
- ガス器具やガスホースなどの点検、掃除をする
- 使わないガス栓にはキャップやカバーを付ける
- ガス器具の不具合やガス漏れが起きた時は、ガス器具の仕様を中止し、換気をしてガス会社に連絡する
など、基本的な事をしっかり守って使えば、事故は防げます。
正しい使い方をしっかり覚えて、日々実行してくださいね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/181be63f.2383612e.181be640.d22b518e/?me_id=1337878&item_id=10000007&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhobbyhouse%2Fcabinet%2Fjrk1a.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
